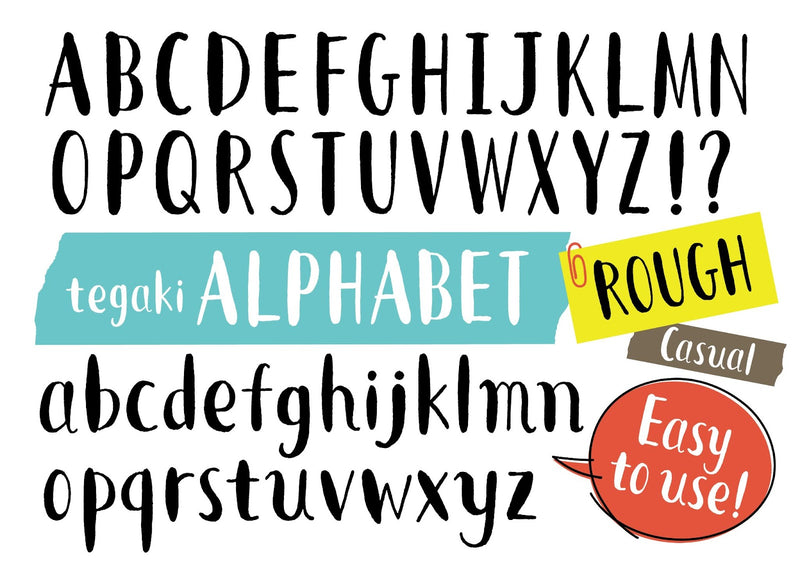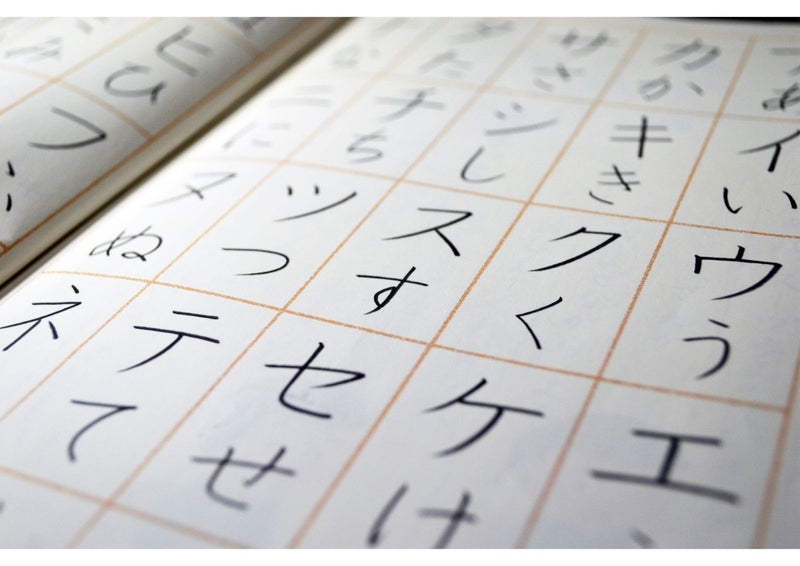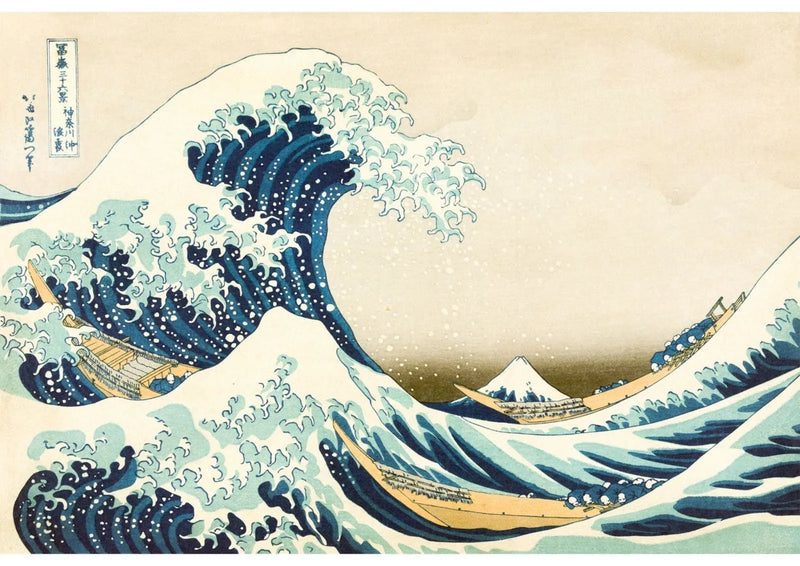印鑑とハンコの違いとは?印章や印影など関連ワードもまとめて解説
公開日:2023.9.19 最終更新日:2024.10.31 宅配便を受け取る際や業務でよく使用する「印鑑」ですが「ハンコ」と呼ぶ人もいるでしょう。 「『印鑑』と 『ハンコ』いったいどっちが正解なの?違いは何?」 そう疑問に思う人は少なくないでしょう。 今回の記事では「印鑑」と「ハンコ」の違いについて解説していきます。印鑑とハンコの違いについて知りたい人はぜひ最後まで読んでみてください。 印鑑とハンコの違い 印鑑とハンコは混合して使われがちですが、実は全く異なるものです。 印鑑は押印後、紙に残る朱肉印のことで「印影」とも呼ばれます。 一方でハンコは銀行印や認印、実印など、棒状の角型や丸型の形状をした本体を指します。つまり朱肉で印影を残すためのものです。ハンコの正しい名称は「印章」といいます。 意味 正式名称 印鑑 紙に押印したもの(朱肉印) 印影 ハンコ 押印するためのもの(銀行印など) 印章 本来はハンコが正しい使い方なのに印鑑という呼び名が浸透していたり、その逆だったりと間違って認識されていることが意外に多いです。 間違っているからといって支障が出ることは少ないですが、いざという時のために憶えておくと良いかもしれません。 印鑑の語源 印鑑の語源は、印影が本当のものかを確認するために使っていた台帳が関係しています。古来、台帳は「鑑(かがみ)」と呼ばれていました。 「印鑑」の漢字に使用されている「鑑(かがみ)」という文字には本来「手本・模範」という意味があります。 印影を確認するための台帳「鑑(かがみ)」をきっかけに、印影そのものを印鑑と呼ぶようになったと考えられています。 印鑑について詳しく知りたい方はこちらの記事もおすすめ↓ ハンコの語源 ハンコの起源には「版行(はんこう)」が関係しています。 そもそも「版行(はんこう)」とは出版物を印刷して発行することを意味しています。古来、書物は木板に絵や文字を彫った版木を用いて印刷(版行)されていました。 鎌倉時代以降、版行(はんこう)は印章の意味でも使われるようになり「はんこう」は音変化して「はんこ」と言われるようになったと言われています。 ちなみに判子という漢字は当て字です。 印鑑の種類について解説 ここまで印鑑とハンコの違いについて解説してきました。 印鑑とはハンコ(印章)を押したときにでる朱肉印のことで、ハンコは印鑑を押すための本体を指します。 つまり印鑑とハンコは全く別物ですが、世間一般では本来の「ハンコ」は「印鑑」という呼び名が浸透しているため、ここからの解説は「印鑑」という呼称を使用していきます。 個人の印鑑の種類 個人が使用する印鑑には「認印・銀行印・実印」の3つがあります。 簡単に違いについて解説します。 認印とは個人が日常で使用する印鑑のことです。認印での捺印は効力が極めて限定的で、国会答弁において「認印は個人の認証としての効力は乏しい」と見解が示されています。 そして銀行印とは、銀行や信用金庫など金融機関に届け出をした印鑑のことを指します。 保険やクレジットカードを申し込む際にも使用するため、金融管理に重要な役割をもちます。しかし役所に登録していないので法的な効力はやはり弱いと言えるでしょう。 法的な効力が強い印鑑が実印です。 実印とは役所に登録した印鑑のことで、公的に認められているため信用力があります。家の購入やローンなど高額な契約の際に必要な印鑑です。 実印は認印や銀行印とは違い、法的な効力をもった印鑑なので管理や取扱いには十分に注意が必要です。 実印について詳しく知りたい方は以下の記事もおすすめです↓ 法人の印鑑の種類 法人印鑑の種類は主に「会社実印・会社銀行印・社印・会社認印・ゴム印」の5つです。 それぞれの印鑑の役割など違いをまとめました。 印鑑の種類 役割や特徴 会社実印 代表者印ともいう。法務局で登録し、重要な契約のときに使用 会社銀行印 法人銀行口座を開設のときに届け出。手形や小切手を切るのにも必要 社印 会社角印ともいう。比較的重要度が低い会社発行の書類に押印する際に使用 会社認印 社印とまとめられることも。日常的な業務に使用 ゴム印 住所印ともいう。制作の際にデザインに決まりはない。住所や社名などが印字されている。パーツが組み換えできるものも。 法人印鑑について詳しくはこちら↓ 印鑑とハンコの呼称はどう使い分ける? シチュエーションによって認識されている呼称があるため、正式名称と違いがあったとしても誤解を生じないために合わせて使用したほうが良いでしょう。 また一般的に「ハンコ」というと連続でポンポンと押すことができるシャチハタとも呼ばれる「浸透印」も含まれ、荷物の受け取りなど重要性の低い押印にも使われています。 公的な書類や業務中の重要書類に押印を求める場合 シャチハタ(浸透印) がNGのシチュエーションでは「印鑑」の呼称を使用する方が望ましいでしょう。 一般的にシャチハタ(浸透印) は「印鑑」だという認識をもつ人は少ないため、シャチハタ(浸透印) 以外での押印を求める際には「ハンコ」ではなく「印鑑」という呼称を使用することをおすすめします。 宅配や回覧板に押印を求める場合 宅配便の受け取りや回覧板の確認印などには「ハンコ」の呼称が浸透しています。押印することで大きなお金が動いたり、信用や責任に関わるシチュエーション以外では「ハンコ」という呼称を使用して問題ないでしょう。 その他書類などでも自筆によるサインが必要なく、印鑑の押印だけで可能な場合もハンコで問題ありません。 ネーム印以外でスタンプ台を利用したスタンプの場合 スタンプ台を使用するスタンプは「ハンコ」と呼ばれることがあります。 そもそもスタンプとは英語で、日本語でいう「印章」や「切手」、ほかにもスタンプを押印する意味をもちます。 バラエティショップなどではゴム印で作成された、さまざまなスタンプが販売されています。スタンプと呼ばれることもありますが、人やシチュエーションによっては「ハンコ」で認識されていることも。 特に小さい子供にとってスタンプは発音しにくいため「ハンコ」を使うほうが良いでしょう。 【まとめ】印鑑とハンコの違いは印影と印章の違い 今回は印鑑とハンコの違いについて解説しました。印鑑とハンコは同じものとして認識されがちですが、全く異なるものです。 「ハンコ」は本体を指し、印章とも呼ばれています。朱肉を付けた印章を紙に押したときに残る朱肉印が「印鑑」で、印影とも呼ばれるものです。 シンプルにまとめると印鑑とハンコの違いは以下のようになります。 ・印鑑=印影(朱肉印) ・ハンコ=印章(本体) ただ一般的には印鑑もハンコも同じものとして使われているため、状況に応じて伝わりやすいほうを使用するのがおすすめです。とはいえ「印鑑とハンコの違い」について知っておいて損はなく、今回の記事がどこかで役に立つと嬉しいです。