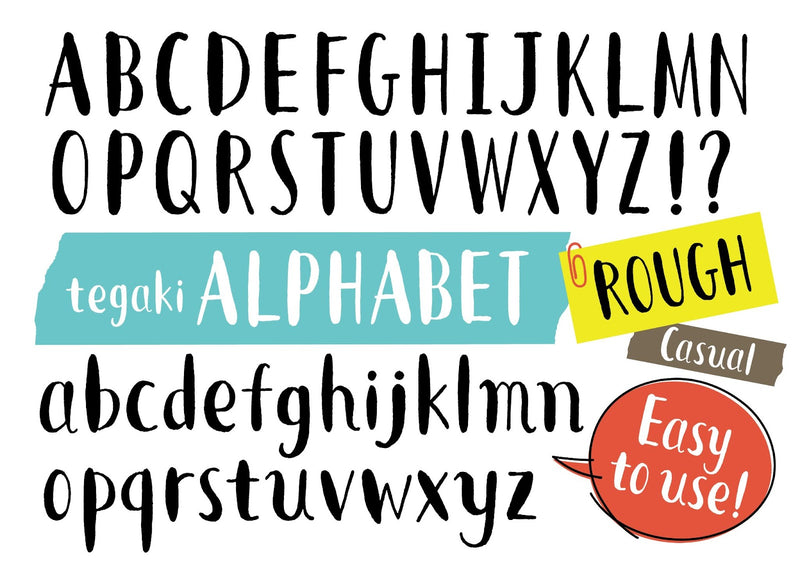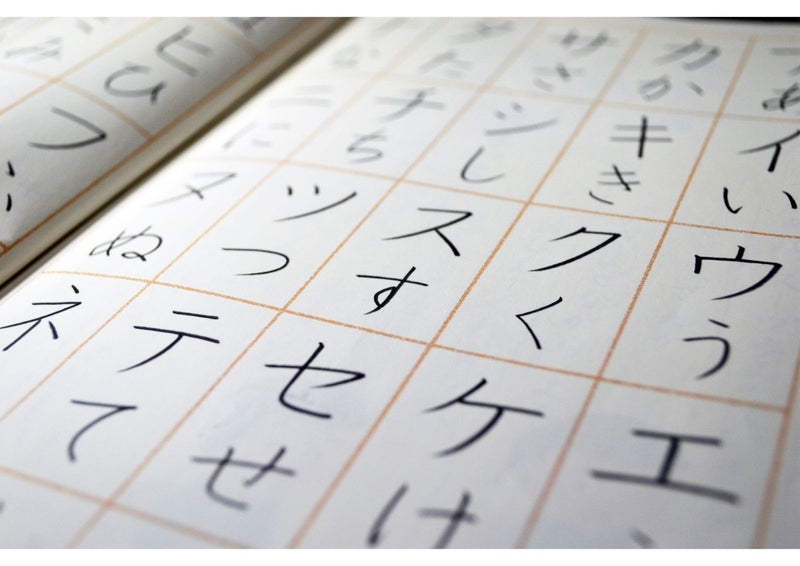みんなに伝えたいペンケース
公開日:2022.9.3 最終更新日:2024.11.2 ペンケースを買う時に、どんなのが良いかと悩んでいませんか?優柔不断で決めらないという方に、ペンケースをカテゴリー毎にご紹介していきます。 立てられるペンケース まずは、立てれるペンケースです。このペンケースの人気が出た理由は、『家でのスペースをより広く使える!』『小スペースを活かせる!』ということです。自宅やカフェで仕事したり、勉強とかしたりする人が増えたことで、小スペースを少しでも活用したいということで、立てれるペンケースは、人気があります。その他の理由として、使用感があります。立つペンケースを使ってみると、こんなに便利なんだっていうことで、使い心地も良いペンケースです。 SMART FIT ACTACT スタンドペンケース – サンビーオンラインショップ ココモ 中身を魅せれる透明ペンケース 次に、中身が見えるペンケースです。このタイプが、近年急激に伸びています。文具が好きな人たちなどは『ペンとかこういう可愛いのがあるんです!』とかこだわって買う人が増えているので、見えちゃって恥ずかしいってことがないんです。今の若い人たちを中心に見えるペンケースっていうのが当たり前になってきていて、何が入ってるかわかるってことも勿論あるんですが、透明ペンケースが人気のある理由として、機能というよりも【中身が魅せれる】という言うキーワードがあります。例えば、スタンプ・万年筆・ガラスペンが人気になってきているので、そういった自分の好きなものを沢山コレクションにされるような方は、一つ一つ独立してゴムバンドとかに留めれるペンケースっていうのが大人を中心に人気が出てきてます。社会人だけでなく、学生の文具好きな人もこのケースを使われています。 株式会社レイメイ藤井https://www.raymay.co.jp/kept/contents/regular/KPF902/lineup.html 丈夫なペンケース ペンケースと言っても本当に幅広くなってきていますが、もちろんキャラクターものもあります。そこに関してはもう本当にそのキャラクターの流行ってる流行ってないっていう感じもあります。例えば、小学生向けの筆入れペンケースですが、マグネット筆入れという商品は、6年間の保証がついています。日本のものづくりってめちゃくちゃ丈夫で、小学校6年間の間で、もし壊れた場合は、保証しますよという形になっててほとんどが壊れないらしいです。 クツワ株式会社 https://www.kutsuwa.co.jp/items/ch201/ スマホがたてれるペンケース 最近出てきているのはスマホがたてられるとか iPad のようなタブレットが立てられるペンケースがあります。これは、本当に便利です!学校がこのコロナ禍でタブレットを無料で配るということの影響が大きく、小学生用のものが特に多いです。もともとタブレットの支給は決まってたことではありましたが、そこを前倒しで国が支給してくれたタブレットを立てて使用するシーンが当たり前の時代になっています。ペンケースも時代と共に変化していることを実感できる商品です。 株式会社ソニック http://www.sonic-s.co.jp/pickup/10282 洗えるシリコン型のペンケース ペンケースのトレンドで言うとあのリヒトラブさん等が出されているシリコン型のシリコンペンケースシリーズが挙げられます。シリコン素材を使った商品は、ペンケース以外では、もともと人気が高かった素材です。実際に使用されている方の話しを聞くと「洗える」と言うのが思った以上に喜ばれていました。 SMART FIT PuniLabo アニマル – サンビーオンラインショップ ココモ このシリコン素材を使ったこの商品は「軽い」「色が変わらない」「収納力が高い」など多くの機能がありましたが、発売当初は「洗える」という機能はサブ的な要素として前面に出していなかったそうです。ところが使用されている方の声から、「洗える」という要素がスゴイという声を多く聞くようになってきたようです。 普通はペンケースに「洗う」要素は必要ないと思います…「洗える」ことが何故よかったのでしょうか? 実は、このシリコンペンケースがヒットしてる理由は、『トラベルグッズ』として非常に使いやすいのです。歯ブラシや化粧品を入れたりするとき、「洗える」ことができるこのペンケースが良い!と注目が集まりました。「化粧筆」「マスカラ」「歯ブラシ」のように、トラベルグッズをマルチに入れられるよねっ!ということで一人が何個も買ったという事例も起きてるぐらいです。この「洗える」と言うキーワードのペンケース、オススメです。 次に流行るだろうペンケース 今後人気が出るペンケースって気になりませんか。ずばり、『大大容量のペンケース』と『ものすごく少ししか入らないペンケース』が流行るだろうと予想しています。 大大容量のペンケース まず、『大大容量のペンケース』ですが、そんなに文房具ばっかり買ってないけどなって皆さん思うかもしれません。しかし、文房具だけじゃなくて、モバイルバッテリーとかイヤホンとか、マウスとか、そういった仕事で一緒に持ち運ぶものも一緒に収納できるペンケースです。なぜ、この『大大容量のペンケース』を予想しているかというと、トレンドになってきてくるのが、ペンケースからバックインバックの間のようなものが増えてきていて、サイズがちょっと大きいけれども、容量が多いといろんなものが収納できるっていうマルチポーチ的なペンケースが、今後は、出てくるかなと思います。そういうマルチポーチ的なペンケースっていうのが、当たり前になってきて、文具入れみたいなものになっていると思うので、修正テープとか、マスキングテープとか服でも小物も今人気があるので、そういったものも収納したい人が多いので、すでにご紹介した「透明ケース」とか、少し大きいサイズのポーチに、スタンプとか入れて持ち歩きたいという人も出てくると、ペンポーチという名前が、ついてるものにペンを入れるかどうかは、使われる方の自由というところがあるので小物を入れる小物入れっていう感覚で最新のペンケースが人気がでるのではないかと予想しています。 ペンケース ブックタイプダブル – サンビーオンラインショップ ココモ ものすごく少ししか入らないペンケース 次に、『ものすごく少ししか入らないペンケース』は、3本しか入らないもので、デジタル社会の中で特に女性に人気のペン幅が小さくなってきているものがたくさんあります。なので、4色のボールペンとシャープペンシルとか、消せるボールペンでも4色とか出てきてますんで、もう数本あれば、十分という方も増えてくると思います。 筆者が愛用している商品 最後に、ペンケース単体っていう考え方ではなくて、筆者が愛用している商品ですが、『手帳カバーにペンケースが付いてる』って言う商品があります。また逆にペンケースなのに違う機能が付いてるって言う商品もあります。例えば、昭和の時代では、あのボタン押したら消しゴムが、出てくるとか、鉛筆削りが出てくるみたいなちょっとロボットみたいなペンケースもありました。こういう発想で、新しいトレンドが大人向けのものも出てきて、スタンプとかマスキングテープとかシールのような今の好きな商品を心地よく、楽しく収納できるって言うペンケースが増えてくると、選択肢も、もっと増えてきて楽しい世界になってくるのかと思います。 合わせて読みたい 筆箱の中身を減らしてシンプルにする方法とは?頭のいい人の筆箱から学ぶ整理術!