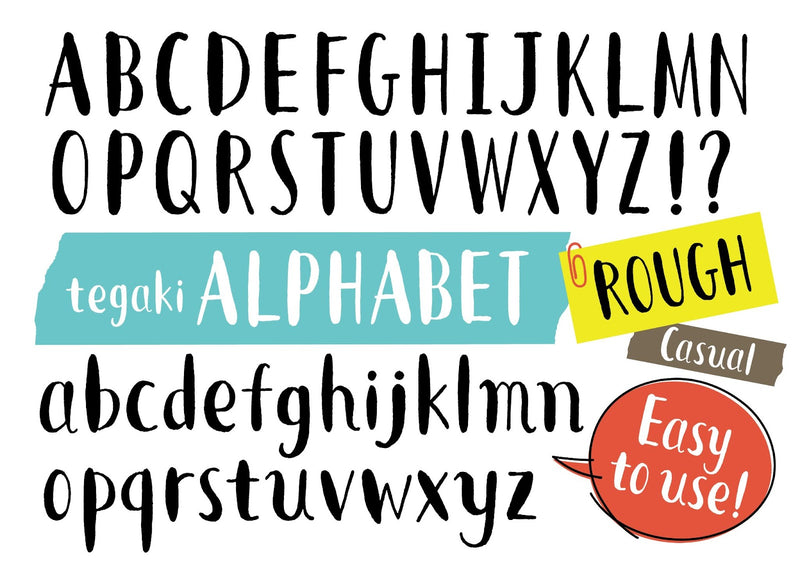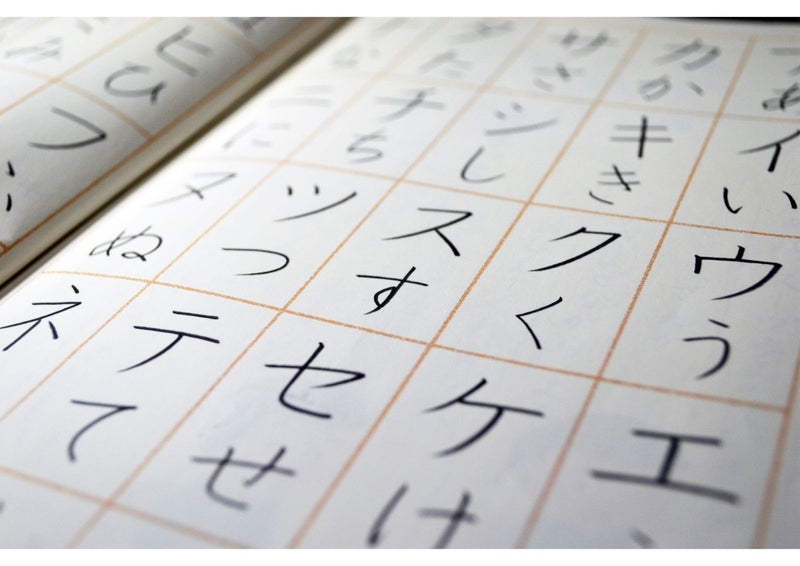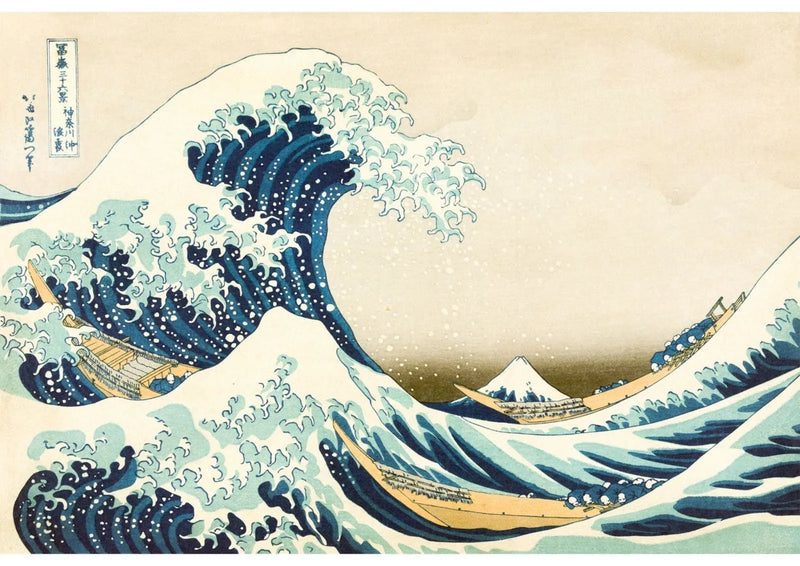社印とは?角印や丸印との違いや使い方を紹介!
公開日:2023.5.12 最終更新日:2024.11.1 法人として扱う書類には、さまざまな印鑑が押されています。このうち、社印とはどのような印鑑を指しているのかをしっかりと理解しておく必要があります。また、社印以外の印鑑の種類や使い方なども覚えておかなくてはなりません。 今回は、法人が扱う社印について、角印や丸印との違いや使い方を紹介します。 社印とは会社名を彫った四角い印鑑のこと 社印とは、会社名を彫った四角い印鑑を指します。サイズが大きく、使用シーンも多いことから、実印と思われている方もいますが、会社の認印です。会社の実印(丸印)は代表者印とも呼ばれており、詳しくは後述します。 社印の主な使用シーンは、社内文書・見積書・請求書・領収書などです。業務で日常的に使われていることが分かります。 社印と似た言葉に「社判」があります。社判とは、会社で使う印鑑の総称です。社印・代表印・銀行印・ゴム印など、会社で使用されるすべての印鑑は社判に該当します。ただし、会社によっては特定の印鑑のことを社判と呼ぶケースもあります。 会社で使う主な印鑑の種類 会社で使う主な印鑑には、角印と丸印があります。ここでは、それぞれの印鑑の特徴を詳しく説明します。 角印 角印とは、文字通り四角い印鑑を指しており、社印と角印は同じ意味で使われます。法人が使用する角印(角判)には、一般的に会社名や屋号などが彫られているため、社印とも呼ばれているのです。 丸印 丸印とは、字のごとく丸い形をした印鑑を指します。印鑑は、以下のように2本セットもしくは3本セットで多く販売されています。 ・2本セット…実印+社印・3本セット…実印+銀行印(割印または住所印)+社印 丸印は、社印よりも法的効力が強い書類で使われます。主に使われる丸印は3種類あり、それぞれ以下のような特徴があります。 会社実印(代表者印) 社印の概要で少し触れたように、会社の実印は代表者印とも呼ばれています。設立登記の段階で、代表者が法務局に印鑑登録した印鑑を指しており、企業名と合わせて役職名が彫られていることが一般的です。 実印の大きさは「1辺の長さが1cm超かつ3cm以内の正方形に収まるもの」と定められています。設立登記以外にも、株券の発行・不動産取引・代表取締役変更など、会社における重要手続きに必要な印鑑です。 銀行印 銀行印は、銀行や信用金庫などの金融機関に届け出をしている印鑑です。法人銀行口座の新規開設や窓口での預金引き出し、手形や小切手の発行など、お金に関わる重要な手続きにおいて使用されます。代表者印は大きさが決まっていますが、銀行印のサイズに規定はありません。 会社実印と銀行印は分けて用意する必要があります。どちらも同じ丸印で、共通して利用できるものではありますが、紛失した際のリスクはとても大きなものです。会社として重要な手続きができなくなり、ビジネス上で大きな問題が生じてしまいます。 会社実印と銀行印は、必ず別々の印鑑を用意し、保管場所も分けることが大切です。 会社認印 3種類の丸印のうち、最も使用頻度が高い印鑑です。印面に会社名だけが彫られており、登録は不要です。 実印の使用場面を限定するため、実印を使わない重要書類への捺印や、社内決裁における役職印などで使われています。 社印の押し方 社印は会社の顔ともいえるため、丁寧かつきれいに押さなくてはなりません。加えて、書類の改ざんを防ぐためにも、正しい押し方を覚えておきましょう。 社印は、会社名・代表者の署名欄・住所などの一部に重ねるようにして押印します。そうすることで、書類の複製が難しくなり、偽造などの悪用を防ぐことができます。 署名欄付近にスペースがなければ、会社名もしくは代表者名の中央付近に押印します。押印場所に迷う場合は、過去に押印した社内書類や取引先の書類などを参考にすることをおすすめします。 押印するときは、捺印マットを使うときれいに捺印できます。朱肉を印鑑につけ過ぎないよう注意し、押すときは「の」の字を書くよう意識して適度な力加減を心がけましょう。 練朱肉・スポンジ朱肉のいずれを使う際も押し方は同様です。 社印を作成する際に意識する点 社印を作成する際は、サイズ・書体・素材の3つを意識する必要があります。それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。 ポイント 1.サイズ 社印のサイズに、特に規定はありません。一般的に使われているサイズは、21mmから24mm程度の正方形です。 角印のサイズは、15・18・21・24㎜の4種類です。大きいサイズはどっしりとした印象を与えますが、社名が短いと余白が多くなってしまいます。反対に、長い社名で小さな角印を作ると、字が読みにくくなってしまうでしょう。 上記の点から、社名の長さとバランスの取れるサイズを選ぶのがおすすめです。験担ぎとして、あえて大きいサイズの角印を選ぶ経営者もいるようです。 ポイント 2.書体 社印の複製を防ぐため、使われる書体は偽造や複製がしにくい書体を選ぶことが大切です。社員に使われる主な書体は、以下の3つです。 篆書体(てんしょたい) 篆書体は可読性が低く、防犯性が高い書体であり、社印に最も多く使われています。日本最古の印鑑とされる漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)の金印や日本の紙幣にも使われており、中国から伝わった書体です。 篆書体で作られた印鑑は、印鑑の枠に文字が多く接触しており、衝撃が加わったり落としたりしたときでも、印鑑の枠が欠けにくい特徴があります。 吉相体(きっそうたい) 吉相体は「印相体」とも呼ばれています。篆書体よりさらに可読性が低く、独特な書体です。社印に使われることは多いものの、文字の特徴から実印登録をしようとすると許可されない場合もあります。 風水や易学でも用いられており、文字が八方に伸びていることから縁起を担いで選ばれるケースも多いです。篆書体同様、印鑑の枠に文字が接しています。 古印体(こいんたい) 古印体は、3つの中で最も可読性が高い書体です。アルファベットの社名でもなじみやすく、優しい印象を与えます。実印や銀行印の書体として使えるほか、認印としても使えることで、汎用性が高い書体です。押印したときに、陰影がきれいに出やすい点が大きなメリットです。 どの書体であっても、名前の最後に「之印」もしくは「印」と入れるのが一般的です。これはおくり字と呼ばれるもので、文字のバランスを取るために入れます。 上記の書体以外にも、近年ではデザイン性が高い書体も増えています。 ポイント 3.素材 社印は長く使うものであるため、素材も重視したいところです。主に以下の3つが使われていることが多いです。 チタン チタンは金属のひとつであり、耐久性が高く、傷がつきにくい特徴があります。ほかの金属類に比べ、朱肉がきれいに付く点が大きなメリットです。 水洗いができ、手入れも簡単なことから、長く使う社印の素材に適しています。ブラストチタン・ゴールドチタン・ブラックチタン・ジュエリーチタンなど、さまざまな種類があります。 黒水牛(くろすいぎゅう) 黒水牛は耐久性が高く、見た目も高級感があるため、社印の素材としてよく使われています。 ただし、直射日光や乾燥に弱い点がデメリットです。黒水牛を選ぶのであれば、保管する場所や方法に十分注意が必要です。 柘植(つげ) 柘植は、アカネ(海外産)と本柘植(国内・薩摩産)との2種類があり、チタンよりも価格を抑えられます。木製のため、縁欠けや摩耗などの経年劣化はあるものの、朱肉がきれいに浸透しやすく、味が出て縁起が良いといわれることも多い素材です。 合わせて読みたい 印材の種類 まとめ 社印は実印とは異なるものの、書類に押印する機会がとても多い印鑑です。これから社印を作ろうと検討している方は、今回紹介した内容を参考に、会社に合った社印を選んでみてください。