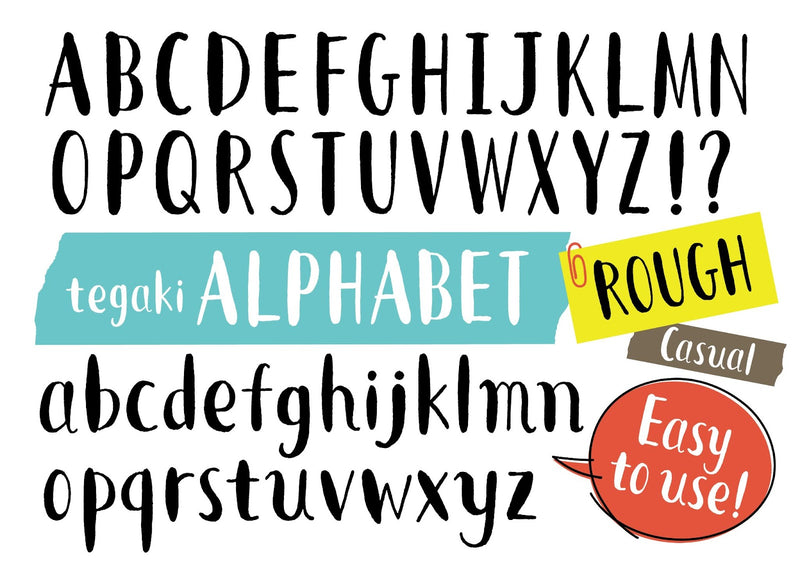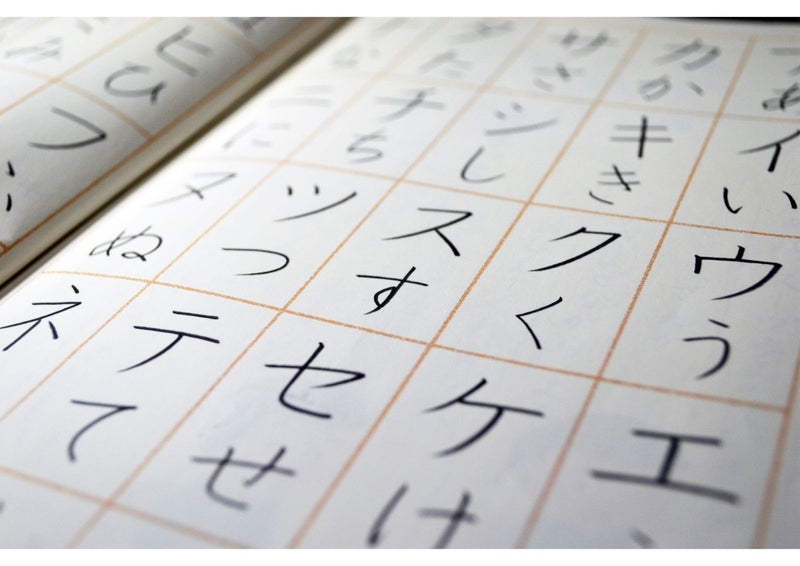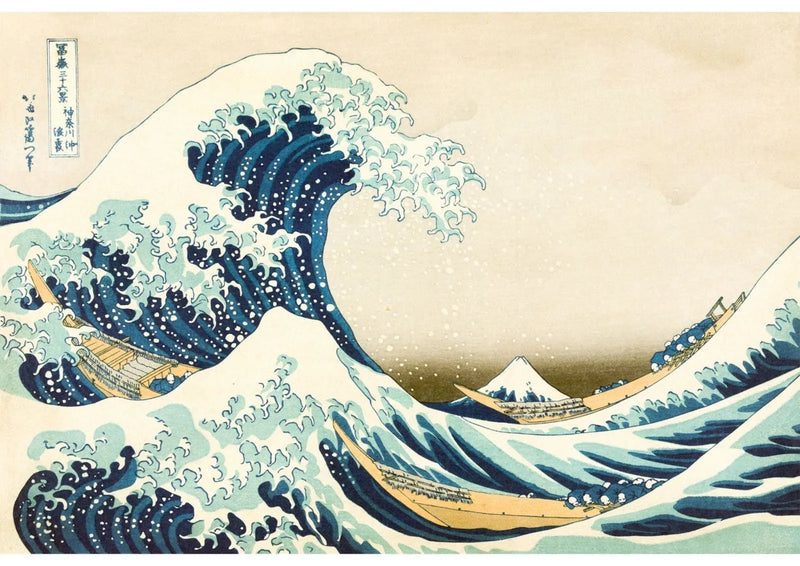文房具のすっきり簡単な収納術!整理整頓が苦手な人にもおすすめ
公開日:2024.7.16 最終更新日:2024.10.30 さまざまな場所で必要となる文房具。 文房具に限ったことではありませんが、きちんと整理して収納しておかないと、必要なときに必要な文房具が見つからないといったことになりかねません。 今回は文房具の収納術と、場所やシチュエーションに応じた収納アイテムの紹介をしていきます。 文房具を収納する前に大切なステップ「分別」 つい増えがちな文房具は、収納の前にまず「分別」することをおすすめします。 「いつか使うかも」「貰い物だし……」「可愛いから」 上記のような理由で、何年も使っていないのに捨てずに置いているものはありませんか? さらに整理整頓が苦手な人は、使っている文房具と使っていない文房具が混ざっている可能性が高いです。次の2つのステップで分別を行ってみましょう。 STEP1.下記の3つに分別します ほぼ毎日のように使うもの 1ヶ月に数回使うもの 半年以上(もしくは1年以上)使っていないもの STEP2.場所やライフスタイルに合わせて分別します 使う場所に応じて分別 持ち歩き用の文房具を選出 使った場所で文房具を放置してしまうと紛失の原因にもなるため、いっそのこと場所ごとに文房具を置いておきましょう。 また出先で文房具を使用する人は、持ち歩き専用のものを選ぶことをおすすめします。 使っていないものやストックの文具は専用の収納ボックスへ 文房具が好きな人や貰ったものを捨てられない人にとって、処分はとても辛いです。 そんな人はストック専用のボックスを作り、普段使う文房具以外はストックボックスへ入れておくようにしましょう。 付箋やカッターといった文具も多い人は、ペン類の文房具と分けておくと取り出しやすいのでおすすめです。 リビングで使う文房具の収納アイデアとおすすめアイテム リビングに文房具を収納する場合は、リビングのインテリアや収納術に合わせましょう。 「見せる収納」と「隠す収納」、それぞれおすすめのアイテムを紹介します。 見せる文房具収納スタンド 画像出典:リモコンラック リモコン収納 スタンド ケース 小物入れ コスメ 文房具 収納 シンプル 北欧 おしゃれ スマホスタンド リビング小物 ホワイト 白 :toolbox-01:モックストア - 通販 - Yahoo!ショッピング ホワイトカラーにチラッと見えるバンブー柄が可愛い文具スタンドです。ボックスの淵は斜めカットになっていて、短いものの出し入れがしやすい仕様になっています。 消しゴムや付箋は手前の方に入れ、文房具やその他ハサミなど高さのある文具は後ろ側に入れましょう。 リビングでよく使うものを選別して、入れすぎないのが見せる収納のポイントです。 購入はこちらから↓ リモコンラック リモコン収納 スタンド ケース 小物入れ コスメ 文房具 収納 シンプル 北欧 おしゃれ スマホスタンド リビング小物 ホワイト 白 :toolbox-01:モックストア - 通販 - Yahoo!ショッピング 片付けも簡単!大容量の文房具収納アイテム 画像出典:ポリプロピレン収納キャリーボックス・ワイド・ホワイトグレー | 無印良品 (muji.com) 電卓やカラーバリエーションの多い色鉛筆やカラーペンの収納も問題なくできる、大容量の文房具収納アイテム。 約幅15cm×奥行32cm×高さ8cmと一見コンパクトながら、電卓やメモ用紙も入れられる幅広いスペースもあり便利です。 持ち手があり使う時のみ収納棚から取り出し、使い終わったらサッと片付けられるのもおすすすめポイントです。 他のインテリアにも馴染みやすいホワイトグレーカラーで、見せる収納としても使えます。 購入はこちらから↓ ポリプロピレン収納キャリーボックス・ワイド・ホワイトグレー | 無印良品 (muji.com) キッチンで使う文房具の収納アイデアとおすすめアイテム キッチンでは文房具を使用しないという人もいる一方で、食材をまとめ買いして小分け冷凍する人にとってはペンやマスキングテープなどをよく使うという人もいるでしょう。 ここでは多用途に使える収納アイテムを紹介します。 冷蔵庫横におすすめ!マグネット付きペンホルダー(4個セット) 画像出典:【楽天市場】マグネット付きハンコ ボールペンホルダー 4個セット 強力磁力 取付け 玄関扉 冷蔵庫へ固定 ホワイトボード 黒板 ロッカー キッチン 台所 宅配便 オフィス 装着したまま 持ち運び コンパクト ハンコ定位置 ハンコホルダー ペンホルダー:Across【アクロース】 (rakuten.co.jp) キッチンで使う文房具の種類は多くない、という人におすすめの文房具収納アイテム。 磁石が付いた伸縮性のある鉄素材のペンホルダーです。使わないときは冷蔵庫など磁石に反応する場所にくっつけて保管できます。 ホルダーは直径17mmのものまで装着可能なので、はんこホルダーとしても使えます。 購入はこちらから↓ 【楽天市場】マグネット付きハンコ ボールペンホルダー 4個セット 強力磁力 取付け 玄関扉 冷蔵庫へ固定 ホワイトボード 黒板 ロッカー キッチン 台所 宅配便 オフィス 装着したまま 持ち運び コンパクト ハンコ定位置 ハンコホルダー ペンホルダー:Across【アクロース】 (rakuten.co.jp) マスキングテープも一緒に入れられる!マグネット付き文房具収納ボックス(3個セット) 画像出典:【楽天市場】マグネットポケット ペン立て マグネット ペンホルダー 鉛筆立て ペンスタンド マグネット 収納 冷蔵庫 マグネット 収納 収納ボックス メッシュ 小物収納 マグネットラック 壁掛け 磁石付き オフィス整理用品 黒 軽量 デスク用 キッチン 冷蔵庫 洗濯機 3点:FINTRUE (rakuten.co.jp) サイズ幅6.8cm×高さ13cm×奥行9cmで、1個あたり1㎏の重さまで耐えられる強力マグネット付き。ペンだけじゃなくマスキングテープやクリップなどさまざまな文具を入れたい人におすすめです。 中に何が入っているのかがわかるメッシュタイプで、探す手間を省けます。底はフラットに設計されているため、テーブルに置いて使うことも可能です。 購入はこちらから↓ 【楽天市場】マグネットポケット ペン立て マグネット ペンホルダー 鉛筆立て ペンスタンド マグネット 収納 冷蔵庫 マグネット 収納 収納ボックス メッシュ 小物収納 マグネットラック 壁掛け 磁石付き オフィス整理用品 黒 軽量 デスク用 キッチン 冷蔵庫 洗濯機 3点:FINTRUE (rakuten.co.jp) 持ち歩きも可能な文房具収納アイテム「ミニマルで暮らしたい人」にもおすすめ 文房具をコンパクトに収納したい人や、持ち歩きしたい人におすすめの文房具収納アイテムを紹介します。 文房具の断捨離をして、本当に必要なもののみを厳選して手元に置いておきたい人におすすめのアイテムです。 こちらの記事もおすすめ☆ 合わせて読みたい 筆箱の中身を減らしてシンプルにする方法とは?頭のいい人の筆箱から学ぶ整理術! 立つペンケース 画像出典:エアピタ クツワ ペン立て 【通販モノタロウ】 (monotaro.com) ミスティブルーやミルキーグレーなど4色から選べる、立つペンケース。空気の力でくっつく吸盤で、揺れにも強くしっかりとデスクにくっつき自立します。 がま口仕様の蓋は全開するとスマホスタンドとしても使用でき、調べものをしたいときに役立ちます。 使用後は底に近い部分を軽くプッシュすると、簡単にデスクから取り外し可能です。 購入はこちらから↓ エアピタ クツワ ペン立て 【通販モノタロウ】 (monotaro.com) 使う時も使わない時も立てておける!文房具収納アイテム 画像出典:ライフスタイルツールファイル A4サイズ ブラック | ライフスタイルツール | ホーム収納 | 収納・整理用品 | 製品紹介 | ナカバヤシ株式会社:アルバム・製本・シュレッダー・情報整理の総合サポーター (nakabayashi.co.jp) ペン以外にもハサミやのり、スタンプ台などさまざまな文具を収納可能なアイテムです。 使うときは写真のように見開き状態にすれば、どこに何があるか一目瞭然で仕事効率化にも役立ちます。 そして使用後は読み終わった本のようにパタンと閉じるだけなので、片付けに時間を要しません。見た目はまるでファイルのようで、他のファイルや本と同じように本棚や収納棚に立てて管理できます。 購入はこちらから↓ ライフスタイルツールファイル A4サイズ ブラック | ライフスタイルツール | ホーム収納 | 収納・整理用品 | 製品紹介 | ナカバヤシ株式会社:アルバム・製本・シュレッダー・情報整理の総合サポーター (nakabayashi.co.jp) オフィスやビジネスパーソン向けの文房具収納アイデアとおすすめアイテム 最近ではオフィスをコンパクトにして、リモートワークを推奨する企業が増えてきています。 フリーアドレスになり、個々の荷物は別途用意されているロッカーで管理し、使う時のみ取り出して使うスタイルを取る企業もあるようです。 そんな人には文房具のアイテム数を減らし、ひとつの箱や持ち歩けるバックスタイルの文具収納がおすすめです。外回りの多い営業職にも向いています。 外回りにもフリーアドレスにもおすすめの文房具収納アイテム 画像出典:【楽天市場】【 送料無料 】 LIHIT LAB. リヒトラブ ALTNA altna ビジネスバッグ ツール バッグ ( ヨコ型 ) バック CORDURA 大容量 おしゃれ 機能性 仕切り A4サイズ カバン 自立 手洗い可能 プレゼント オフィス 工具 アウトドア 車 バイク ツールバッグ(diy):COCOMO 楽天市場店 (rakuten.co.jp) 多数の小ポケットのほか、ペンを指して収納できる箇所も付いているので、収納アイテムとしてもバッグとしても重宝します。 収納棚からも取り出しやすい、側面にハンドルが付いた仕様になっています。 A4サイズのファイルも余裕で入れられるので、資料を持ち歩く必要のある、外回りにも重宝します。 素材は重さや汚れに強いポリエステルを採用。持ち運び、持ち歩きしやすい軽さも人気のポイントです。 購入はこちらから↓ 【楽天市場】【 送料無料 】 LIHIT LAB. リヒトラブ ALTNA altna ビジネスバッグ ツール バッグ ( ヨコ型 ) バック CORDURA 大容量 おしゃれ 機能性 仕切り A4サイズ カバン 自立 手洗い可能 プレゼント オフィス 工具 アウトドア 車 バイク ツールバッグ(diy):COCOMO 楽天市場店 (rakuten.co.jp) デスク周りの文房具をすっきり簡単に収納可能アイテム 画像出典:haconia(ハコニア)卓上トレーA5 グレー | haconia(ハコニア) 卓上トレー | ホーム収納 | 収納・整理用品 | 製品紹介 | ナカバヤシ株式会社:アルバム・製本・シュレッダー・情報整理の総合サポーター (nakabayashi.co.jp) 少数精鋭の文具で作業する人におすすめの収納アイテムです。紙製で325gと軽く、シンプルでおしゃれなデザインもおすすめポイント。 3段式で2つのスライドトレーが付いており、クリップや定規といった小物からノートなどの大物文具をざっくりと分別し収納できます。 サイズは幅25.3cm×奥行17.2cm×高さ7.5cmで、デスクの上に置いても邪魔になりにくいサイズです。デスクの上を常に綺麗に保ち、片付けも一瞬で終わらせて退勤できます。 購入はこちらから↓ haconia(ハコニア)卓上トレーA5 グレー | haconia(ハコニア) 卓上トレー | ホーム収納 | 収納・整理用品 | 製品紹介 | ナカバヤシ株式会社:アルバム・製本・シュレッダー・情報整理の総合サポーター (nakabayashi.co.jp) 整理整頓が苦手な人は文房具を整理しない収納もあり! 整理整頓が苦手で、何度もチャレンジしては失敗を繰り返している人におすすめなのが、整理しない収納術です。 ペンだけでなく、ハサミやのり、電卓など使う文具を整理せずにすべて同じ箱にいれます。 ポイントは「収納するアイテムが全部入るサイズの収納ボックスを選ぶ」という点です。 ただし手元にある文具を全部入れようとすると膨大な量になり、とても大きい箱が必要になります。 大切なのは冒頭でもお伝えした「分別」です。そして、普段「使わないもの」は入れないということも気を付けましょう。 そして収納ボックスは蓋付きのものをおすすめします。文房具はなぜか徐々に増えてくるため、蓋ができなくなった時点で長期使用していない文房具の処分を検討しましょう。 【まとめ】文房具のすっきり収納には分別がポイント! 文房具は小さく比較的安価で購入できるため、つい増えがちなアイテムです。 そしてきちんと収納できていないと使いたいときに見つからず、無駄に購入してしまうことにもなりかねません。 文房具はよく使う場所でそれぞれ正しく収納しておきましょう。 整理が苦手な人は文房具用の収納ボックスをひとつ作り、定位置に置いておくだけで探すということがなくなります。